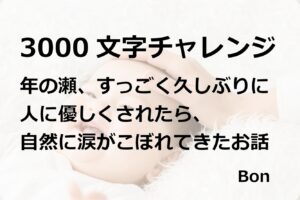3000文字チャレンジ|納豆
刑「どうしてここに連れてこられたか、分かってるな?」
ボ「ええ、分かっているつもりです」
刑「今日、お前を担当する斎藤だ。こっちは鈴木、記録係だ」
ボ「はい、よろしくお願いします」
刑「あと、ここでの会話はすべて録音されている。発言には気をつけるんだな」
ボ「ええ、刑事さん。でも聞いてください。アレは事故だったんです」
刑「おいおいおい、お前、事の重大さが分かっているのか? 事故の一言で済む話じゃない」
ボ「いや、違うんです。違うというか、あの日はただ、いつも通りに登校しただけなんです。
僕だってあんなことになるなんて知らなかった」
刑「お前、今いくつだ?」
ボ「17です」
刑「若いな。俺にも同じくらいの娘がいる。こういうとき、親がなんて思うか分かるか?」
ボ「いえ」
刑「正直にすべてを話し、やり直して欲しいってことだ」
ボ「だったら…!分かるでしょう。僕は嘘をついていない。ワザとじゃあないんだ」
刑「そうかもしれない。ただ今回のケースはやりすぎだ。覚悟はしておけ」
ボ「そんな、僕はどうしたら…」
刑「だからこそだ。全部をありのままに話せ。あと、先に言っておくが、お前はたぶん終わりだ。そして俺はただの仲介役。今後を決めるのは法の役目だ」
ボ「なんてことだ…なんてことだ…」
刑「落ち着いて、質問に答えろ。どうして弁当のおかずに『納豆』なんて持ってきた?」
ボ「知らなかったんです。昼休みにお弁当包みを解いたら、あの納豆のパックが入っていました。すごい存在感だった」
刑「どんなパックだ?」
ボ「普通の白いパックです。発泡スチロールの。たぶん3個入りで、四角いやつ」
刑「銘柄は分かるか?」
ボ「いえ、でも『におわなっとう』ではなかったと思います」
刑「当然だな。もしそうなら、こんな事にはなってない。救急車だって出動しなかっただろうよ。で、他には何があった?」
ボ「他には何も。納豆、そしてライスだけです。刑事さん、僕は本当に知らなかったんだ。誰が好き好んで、学校に納豆なんて持ち込みますか? だってそうでしょう? 高校生なんてのは、悪目立ちしたらお終いだ。すぐに笑いの種にされてしまう。なのに納豆だなんておいしいネタを、わざわざ持ち込むなんて馬鹿げている。アレは僕が入れたものじゃあない」
刑「納豆は、別の誰かが入れたとでも言いたいのか?」
ボ「そうです。きっと母だ。他に考えられない」
刑「母親の仕事はなんだ?」
ボ「主婦です」
刑「専業か?」
ボ「ええ、そうです」
刑 「ばかを言うな!専業主婦が息子の弁当に、納豆をパックのまま突っ込むとでもいうのか?」
ボ「信じてください、刑事さん。十分にありえることなんです。なぜなら最近まで、僕のあだ名は『リューイーソー』だったのですから」
刑「何を言ってる?ちゃんと分かるように話せ」
ボ「先月のことです。いつものように弁当箱を開けたら、そこには真ん中からへし折られたキュウリが、そのまま入っていたんです。丸ごとですよ?」
刑「なんだと? ライスはどうした?」
ボ「ありません。ライスボックスにもキュウリです。同じ手口でへし折られていました」
刑「味噌はどうだ?」
ボ「味噌も、マヨもありません。箸すらついていないのです」
刑「なんてこった。完全な緑一色じゃないか」
ボ「ええ、そうなんです刑事さん。ウチの母は、心にそういう闇を抱えている。だから、おかずの代わりに納豆がひとつ添えられていても、全く不思議はないのです」
刑「だからといって、お前の犯した罪が帳消しになるわけじゃない」
ボ「なぜですか!あれは完全に不可抗力だ。お弁当包みの中に何が入っているかなんて、外から分かりっこない。もし事前に知っていたなら、それをすり替えることだって出来たんだ」
刑「では訊こう。どうして、納豆のパックを開けた? お前が教室でアレを混ぜ混ぜなんてしなければ、こんな惨事は防げたハズだ」
ボ「ああ、刑事さん。あなたも日本人なら分かるはずだ。半合ものライスを、おかずも無しに食べきるなんて不可能だ。あなただって、山盛りのライスを目の前にしたら、きっと途中で箸が止まるはずだ。それが人間というものです」
刑「続けろ」
ボ「僕だって、頑張ったんです。10口までは耐え抜いた。だが限界でした。でも手を伸ばせば、そこにはおかずになる白いパックがある。あれは悪魔の誘惑でした。簡単に抗えるものじゃあない。誰しもが強い人間ではないんだ。」
刑「冬の教室は半分密室だ。そのことは頭になかったのか?」
ボ「当然ありました。でも、他に選択肢はなかったんだ。だってそうでしょう? 半分以上も残ったライスを残飯にするなんて、許されることじゃあない。『米の一粒は汗の一粒』なんです。生産者の顔を思い浮かべたら、とても残すことなど出来なかった。教室で納豆を混ぜ混ぜすること。あれは、そう、『感謝』だったんです。僕の、農家のおじさんに対するリスペクトに他ならなかったんだ」
刑「罪の意識はなかったと?」
ボ「正直、わかりません。ただ、徐々に騒ぎが大きくなる教室のなかで、僕は独り、不思議な達成感に満たされていた気がするのです」
刑「お前のその狂ったリスペクトが、翌日の理科室を地獄へと変えたんだぞ」
ボ「ああ、刑事さん。それこそ事故というものです。どうして混ぜ混ぜの当日に、理科で培養実験があるなんて知ることができましょう。僕は神じゃあない。目に見えない小さな菌が手からこぼれ、栄養たっぷりなシャーレの中に混入するなんて分かるはずがない」
刑「納豆を食べたら、手を洗う。これは国民の義務だ」
ボ「当然です。僕は念入りに洗った。でも納豆菌はある種の生物兵器だ。縄文の時代から改良され続け、恐るべきタフさと増殖能を持っている。いち高校生の手洗いなんかで太刀打ちできるものではありません。それに僕の納豆を食べたのは、他に3人いた。この中の誰が犯人かなんて、誰にも分かりっこない」
刑「なぜそいつらは、お前の納豆に手を出したんだ? あれは30分に一度は分裂する化け物だぞ」
ボ「そんなことは本人たちに訊いてください。単に納豆が好きだったのか、それとも悪ふざけなのか、他人の心の中なんて僕には分からない。そもそもティーン男子のおふざけに、いちいち理由なんてないでしょう。彼らはケダモノだ。風の強い日はスカートがめくり上がるのを期待して、校門近くで不自然なまでに歩行速度が遅くなる。そんな愚かで哀れなケダモノでしかないんだ。あなただって、そんなことくらい知っているはずだ。そうでしょう?」
刑「混ぜ混ぜの翌日、地獄の釜の蓋を開けたのは誰だ?」
ボ「理科教員です。シャーレを保温していた培養器。その扉には鍵がかかっていました。イタズラ防止のためでしょう」
刑「つまり、35℃の培養器の中で、シャーレの納豆菌はぬくぬく育っていたって訳だ」
ボ「ええ、そうです。時間にして24h。納豆菌には48回も分裂するチャンスがあった。条件さえ合えば10の48乗、つまりは280兆個となっていたハズです」
刑「で、開けた先生はどうなった?」
ボ「死にました」
刑「死んだ?」
ボ「ええ、彼の『クールなキャラ』が死にました。扉を開けた瞬間、彼はあまりにも強烈な臭いに『アババァァァ!』と叫び、そのあと小指を突き上げて教室内を走り回ったのです。人は極限状態で『アババァァァ!』と叫ぶ。本能の咆哮です。恐ろしい光景でした」
刑「小指はどうしたんだ?」
ボ「慌てて扉を閉めるとき、挟んだのです。何か『イケナイ音』が聞こえた気がします」
刑「質問は以上だ。何か言い残したいことはあるか?」
ボ「1点だけ。朝食で納豆を食べるなら、食事後に洗顔をした方がいい。さもなくばマスクが、納豆菌に汚染されてしまう。そうなったらお終いだ。奴らは何度洗濯しても蘇るんだ」