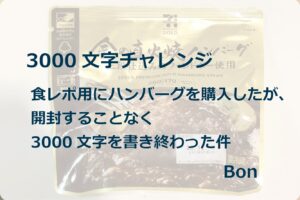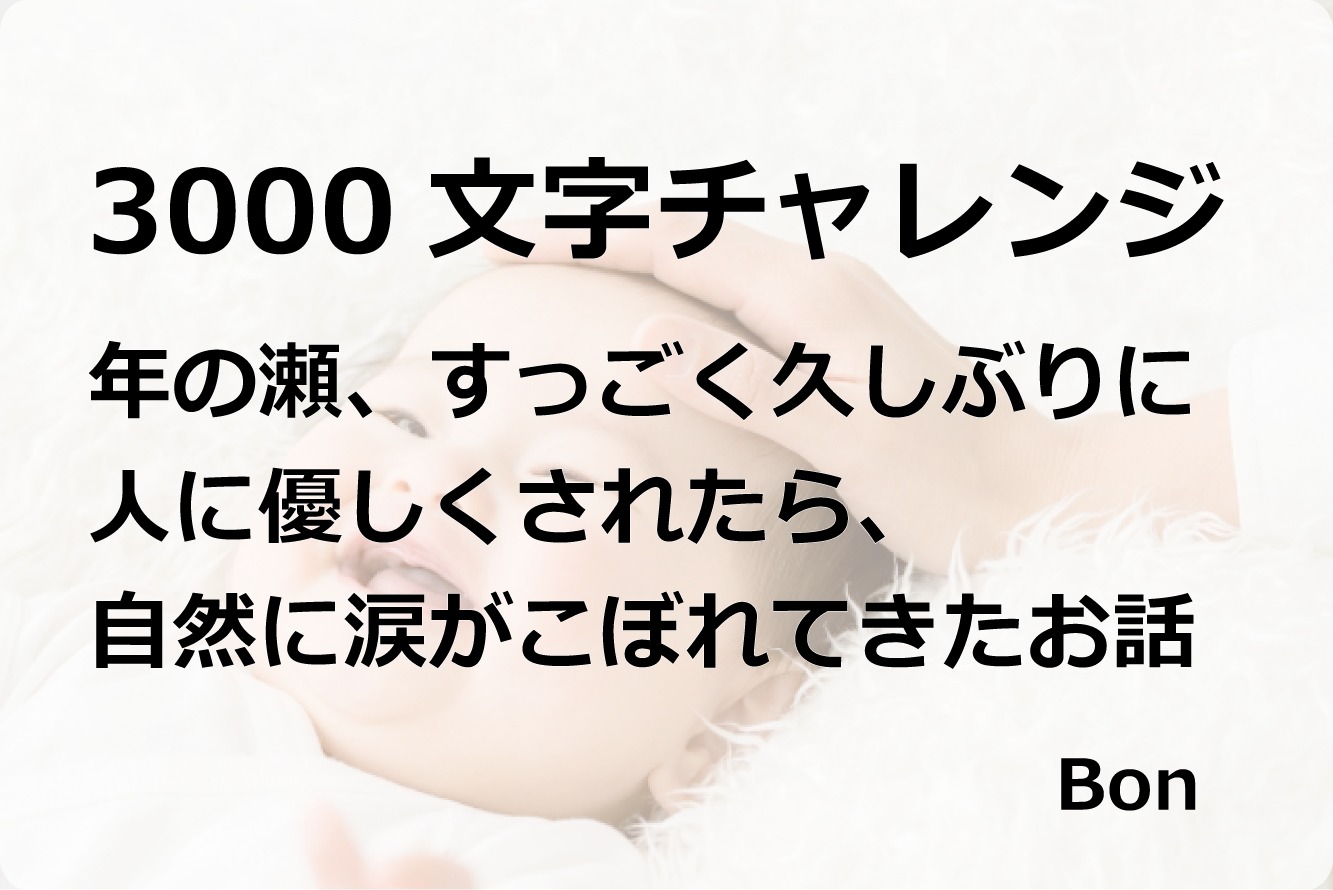3000文字チャレンジ|和
今回のタイトルは「和」です。年の瀬に和やかなひと時を送れるのは、とても素敵なこと。そして和やかさとは、人の優しさに由来するものではないでしょうか。年の瀬に、そんなほんわかストーリーをお届けしたい。そんな一心で書きました。少なくとも、最初の2分は、、、
優しき人よ
「大丈夫、大丈夫だから、ねっ?」
姿は見えないが、優しく語りかける女性の声。背中をそっとさする優しい感触。これは、同じ人物によるものだろうか。触れている手の平からは、ほのかな温もりが伝わってくる。
むず痒いような、恥ずかしいような。こんな複雑な感情を覚えるのは、いつ以来だろう。いや、そもそも他人に優しい声をかけられたのだって、いつが最後だったか思い出せない。ましてやそれが、今日会ったばかりの見知らぬ人とは皮肉な話だ。
思い返せば、退職するとき、日本を発つとき、帰国のとき。いずれの機会でも別れの言葉は交わしたものの、そこに内包されていたのは優しさではなく、激励だった。
いや、あれはそんなポジティブなものでは無かっただろう。自由気ままに新天地へと飛び出していく。そんな私に対する妬みや嫉み、彼らの目にはそんな感情が透けていた。
「うまく逃げやがって」。最期にそう言った元上司の口元だけが笑った顔は、実に歪んだヒトの本性を体現していて、とてもとても醜いものに見えた。
当の辞めゆく本人は、安定した生活を捨て、明日から不安が止まぬ日々を送るというのに。羨ましいことなど微塵もない。
ともかく、そうした日陰の道を進むうち、私は人に甘えることが出来なくなっていた。弱さを見せたら取って食われる。社会は一度でもルールを逸脱した者に容赦をしない。
SNSがいい例だ。配慮が足りない、言い間違えた、教科書的には不正解。こんな些末な過ちですら、世間というのは容赦をしない。
何処からともなく「正義」を掲げた輩が現れ、当の本人よりも、遥かにモラルに欠けた「正しい言葉」を振り上げて、徹底的に打ち下ろすのだ。
友情、親睦、絆。これらが成立するのに肩書が必要なことは、意外なまでに世間に浸透していない。
そんなどこまでも現実的な世間の片隅で、ただただ上から目線の糾弾をやり過ごしていた私は、まるで警戒心の強いノラ猫だった。
他人には優しさを期待しない。他人には依存しない。それらは己を弱くしてしまう。
世の中は、圧倒多数が性悪説だ。そんな態度で辞職以降を生きてきた。
なのに一体、どうしたことだろう。この優しい手の平、優しい言葉は、どうして私の心にこうも響くのだろう。
もしかしたら独りで強がりながらも、ずっと私は信じていたのだろうか。見返りを要求しない、ただただ純粋な優しさが存在するということを。いつかはその優しさに出逢える日が来ることを。
現に今もこうして無償の温もりに、私は成すがままにされている。身をよじるでなく、すり寄るでなく、ただただジッと優しい手に晒されている。まるで撫でられながらも姿勢を崩さず、ジッと警戒しているノラ猫みたいだ。
ただ不思議なことに、それを拒絶する気持ちはどこにもなかった。むしろ居心地の良さを感じていたのだ。
ああ、私はいままで何を意固地になっていたのだろう。拒絶していたのは世間ではなく、私の方だったのかもしれない。
どうやら私は老いたらしい。そんな皮肉で照れを誤魔化すくらいしか、気持ちの整理がつかないのである。
そんな心変わりを始めた私に、もっと驚くことが起きていた。
ツゥ~っと一筋、背中に感じる温もりよりも、わずかに熱を帯びた雫が頬を伝って流れていった。これにはいよいよ驚いた。いや、戸惑ったというのが近いだろう。
見返りを求めれば自分が傷つく、優しくされたら弱くなる。独りで生きぬくことを決意した数年前から、ずっと私はポーカーフェイスのノラ猫だった。
感情よりも合理性、人情よりも合理性、徹底的に情を否定して生きてきた。
そんな私が人前で泣いている。
見知らぬ人に手を添えられて、顔も拭わず、ただただ静かに泣いている。「人は独りでは生きられない」。そんな使い古した定型句など、軟弱だ。そう突っ張って生きてきたのに。
どうやら私は間違っていた。この涙がその証明だ。見知らぬ貴方。貴方は大切なことを教えてくれた。「人は独りでは生きられない」。そう、私もひとりの人の子だった。
どうかお礼を言わせて欲しい。おそらくここで礼も返せぬ捻くれ者なら、私は本当の意味で畜生道に落ちるであろう。
大丈夫。私は大丈夫だ。優しき手の主よ。「ありがとう」。そうして私が感謝を伝えようと、視線をそちらへ向けた、その時だった。
うぶぉえぇぇ、ぐぇぇあぁぁつっぅぅぅぅんんっぅ!!
そんなラスボス並みの尋常ならざる断末魔が、私の喉から、いや腹からか? もしかしたら食道付近か、気管支あたりか。とにかく、身体の内から轟 (とどろ)いた。
叫びは部屋の空気をビリビリ震わせ、間髪入れずに自身の鼓膜も震わせた。
感動、涙、そして他人への感謝をしたのは久しぶりだが、さらには絶叫したのもよっぽど久しい。今日はつくづく、自分の隠れた一面に驚かされる。
長年、人間なんぞをやっていれば、きっとそんな因果な日だってくるのだろう。
そんなふうに己を振り返ることで、私は冷静な自分を取り繕おうと試みていた。とはいえ先の絶叫は、無かったことにするには、あまりに印象的な一撃だった。
実際、私は咆哮を発した本人でもあったが、その神懸かった悲痛な響きに、これ以上なくドン引きしていた。
人の身体というのは、こんなにもおぞましい音を発する機能を持ち合わせている。そんな事実に対するドン引きだ。
なるほど。どうやら私は「えずき」というものを誤解していたようだ。あれは声帯を震わせて「発声」するものではなく、五臓六腑を総動員した「慟哭」なのだ。
深掘りすれば、「言の葉」ではなく、「叫び」に近い。動詞に変換するなら「吼える」が適するワードだろう。
久方ぶりの涙を流す私は次に、ノラ猫を気取ったアイデンティティの崩壊を迎えていた。
「たひゅけて (助けて)、どうか、たひゅけてくだひゃい、、、」。
数分前、確かに私は孤高の存在を気取っていた。だが今はどうだろう。涙どころか鼻水までもをダラダラ流し、助けを求める憐れにまみれた芋虫だった。
だがそんな私の切なる願いは、およそ人の声とは違った異音となって、外の世界に飛び出した。
うぶぉえぇぇ、ぐぇぇあぁぁつっぅぅぅぅんんっぅ!!
はぐぅ、はぐぅぇぇああ、ああん!?
「ひと思いに殺してくれ」。穏やかな日々を愛する私は、自分に一生縁がないと確信していたフレーズに、これ以上なくマッチしている状況下にいた。
上部消化管内視鏡検査、通称「胃カメラ」。にわか仕込みのマゾヒズムを識別するのに、これほど適した技術はないだろう。
ああ、私はマゾではなかった。嬉しいような、それでいて残念なような気持ちに困惑しながら、私は一つの後悔に身を焼かれていた。
どうしてあの時、処方された「麻酔キャンディー」で遊んだのか、と。
麻酔キャンディー、それは胃カメラを口からグリグリされる者に対する、唯一無二の科学の救いだ。
液体麻酔を「あめ玉」状に凍らせたそれは、口の中で溶かしつつ、喉に流すように指導される。
これにより「えずき」のトリガーである舌根が麻痺をして、結果、吐き気が抑制されるのだ。
しかし、この「あめ玉」を含んだその瞬間、私は口腔内に広がるほのかな苦みに囚われていた。はて、この味は何の食べ物だっただろうか、と。
どこか田舎の郷土料理か、異国で試した昆虫食か、はてさて、どうにも思い出せない。
なかなか開かない記憶の引き出しをこじ開けようと、私は指導をすっかり忘れて、コロコロ、コロコロ、舌の上にて転がし続けた。
だが相手は「麻酔」である。その味を確かめようとすればするほど、味覚がボンヤリ鈍ってくるのだ。
もはや私は、溶かしたそれらを飲み込むことすら良しとせず、ただただ苦味の判別作業に勤しんでいた。
そうしてあめ玉が無くなる頃には、私の舌はすっかり麻痺し、「サ行」と「ハ行」を言えない身体となっていた。
胃カメラなんて怖くない。鼻から入れれば怖くない。いやいや、私は口からなのだ。
嘔吐反射は眠っているから怖くない。いやいや、バッチリ、クッキリ起きています。
そうして私の咆哮は、その後も6度にわたって響き渡った。「bonさんは少し、嘔吐反射が強いようです」。
そんな有難くもない評価を授かり、私はお口の処女を失った。