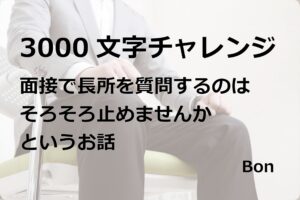3000文字チャレンジ|神様
久しぶりの3000文字チャレンジである。
最後に3000文字を書いたのは2020年の大晦日、よって半年ぶりのチャレンジだ。いつのまにやら今年は半分が過ぎ去っている。時の流れはホントに早い。
と書き出してみたものの、今年の前半を振り返ってみたところで特筆することは何もない。しいて言えば我が身に多少の変化、いや、とある事変が起こったくらいであろう。
事変というか、もはや運命
とある事変。これはヒトという生物種が義務付けられた運命だろう。いわば老いに類する、逃れられない運命ともいえる。
ヒトはいつかは必ず死ぬ。このような、やがて訪れる真理の一つに他ならない。
そして残念ながら、こうした運命の多くは過酷で残酷、受け入れがたいものである。
自分だけは違うはず、そう言って誰しもが目を逸らし、だが内心ではその到来を察知し、畏れ、それでも最期の時まで目を逸らす。
そんな歓迎されざる訪問者。これが予想よりも少々早く、他の人より少々早く、私のもとに訪れただけなのだ。
「お気にのジーンズが入らない」という運命が。
お気にのジーンズが入らない
この現実に直面した際の衝撃がお分かりいただけるだろうか。とてもでないが、私には文字に変換できそうもない。いや、できるはずがないのである。
なぜならあの瞬間、私の言語野は完全に機能を失っていた。今でも記憶はあやふやなままなのだ。
改めて言ってみよう。「ジーンズが入らない」と。いやこれでは語弊があるかもしれない。正確に描写すれば、足は入ったのだ。両方ともだ。
とはいえ、外観上は「めり込む」が適した風情だったと思う。それでも足は入った。ついでにケツも一応は、入った。
ただし、ファスナー上部に位置するボタンばかりはどうにもいけない。どう頑張ってもアレは留まらなかった。
今にして思えば、後先考えずに無茶をすれば、くだんのボタンは留まっただろう。ただ、その代償は大きかったに違いない。きっとモザイク必須の何かが、身体の内より飛び出す寸法だった。
それに母によれば、私は物心が付くその以前、そこらの小腸を手術したことがあるらしい。おそらくヘルニアではないかと推察するが、いずれにせよ無理は禁忌の部位といえるだろう。
しかも、世間において私は常識人として通っている。ジーンズが理由で119番をコールするのは迷惑だ。それくらいは認識している。私は常識人なのだ。
それにしても何たることだ。先月までは確かにボタンを留められた。そう、キッツいながらも留められたのだ。だが今は全くもって不可能だ。
これは本当に同じ服飾だろうか。とかく、反対側のボタンホール、そこに到る距離があまりに遠い。
こんなもの、傍からみればわずか数センチの距離にしか見えないはずだ。ところが、「ジーンズを履く」という制約を受けた途端、この数センチは特別な意味をもってしまう。
そこにはマナー、常識、そして絶望の影がチラつくのである。これらのプレッシャーを背に、最初は苦笑まじりに取り組んでいた私だが、いつしかそれは焦りに代わり、ゆっくりと、しかし確実に絶望の気配が迫って来るのを感じていた。
あれから5分は経っただろうか。なおも拡がる絶望の濃霧は、ついに私の脳から這い出し、やがて脂汗と混じって視認が可能となった。
気づけば私は草原に立っていた。ステップ気候特有の、緑あふれる大海原が拡がっている。ああ、私はここを知っている。かつて訪れた大モンゴルの草原だ。
私は死んだのだろうか。ジーンズが履けないショックで死んだのだろうか。そんな状況理解に努める間にも、私の口から、鼻から、噴き出る霧は、みるみるうちに辺りを包む。それは徐々に馬の姿を取り始めた。
ああ、この馬は、きっと神馬 (しんめ)に違いない。モンゴルのおっさんが力説していた黒く輝く神の使い、きっと御告げを届けにきたのだろう。
「イマヤ、オマエハ、ブックブク」と。
そして一方的なディスりを終えた御使いは、ひとたび鋭く嘶 (いなな)くと、次の瞬間駆けだした。それはモンゴルの大地を遥か彼方に向かってぐんぐん、ぐんぐん疾走してゆく。
やがて地平に至ったそれは、蒼天と一つに交わり宇宙に昇る。おっさんの口伝の通りだ。馬はそのまま星となり、夜には優しく煌めくのだろう。
次の瞬間、私は正気に返った。どうやらジーンズが「入らない」ショックのあまり、白昼夢をみていたらしい。記憶が混雑している。
だいいち、私はモンゴルに行ったことがない。
先ほどのビジョンも、過去の記憶がフラッシュバックしただけだろう。おそらく小学校で読んだ「スーホの白い馬」の一場面に違いない。
とにもかくにも大混乱
先ほど、読者諸氏を置いてきぼりにパニックしたこと、これについては謝罪したい。とにもかくにも、ジーンズが「入らない」。これは大混乱をきたす大ごとなのだと伝えたかった。
さて、なんとかモンゴルから帰還した私であったが、例のすき間は相も変わらず顕在だった。
困った。これでは外出できない。このジーンズは服飾としてのアイデンティティを失っているのだ。
仮にこのまま外出を強行しようものなら、どこぞの不幸な淑女が悲鳴をあげるに違いない。
理由は聡明な読者諸氏なら分かるだろう。そう、偶発的かつ不可抗力のアクシデントにてチャックが下がり、淑女の眼前にて私の可愛いスーホが「コンニチワ」をするからだ。
僭越ながら、こうした間の悪さには自負がある。自慢になって恐縮だが、私は引きの強さに裏切られた記憶がない。
一例としては、大学時代に付き合った女性が挙げられるだろう。彼女は交際して間もなくに誕生日を迎え、その翌月、さらにはその翌月にも誕生日が訪れると主張する、まっこと稀有な存在だった。
そう、彼女は毎月5日に歳を重ねる、ただならぬカルマを背負った人物だった。この業の根深さは相当だ。きっと前世では多くの人を殺めていたに違いない。
そして、こんなレアっ娘とエンカウントできるのは、私が類まれなる「持った」人物であることの証明に他ならない。
話を戻そう
ジーンズが「入らない」。あの悪夢の瞬間、人は一体何を思うのだろうか。
ここからは、その体験を綴ってみよう。これは後悔の記録であるとともに、人は歴史に学ばない、そんな教訓の裏付けになることだろう。
前述したとおり、「入らない」人々の多くはその瞬間を迎えるかなり前から、肥満の予兆を感じている、はずだ。
だが、それが目を背けきれない現実に変わるまで、見てみぬふりをするのが普通だろうと私は思う。
少なくとも今回のケースで、私は数ヵ月にわたってブックブクの予兆を無視し続けた。
この数ヵ月のあいだは、現実逃避のワードが相応しい。ブックブクなんて都市伝説。ウチは太らない家系だから大丈夫。そんなご都合主義を幾重にも着込み、ついでに脂肪も重ね着し、私は現実からただただ目を逸らしていた。
そればかりか、近頃はTOECの勉強に勤しんでいる。きっと脳ではカロリーを大量消費しているに違いない。ならばここはカロリー摂取が必要だろう。
そんな訳の分からないゴリ押しを武器に、積極的にボリボリ、バクバクしていたお茶目さんがそこに居たのだ。
当然ながら、これら屁理屈には何の根拠もない。端的にいえばドアホといえる。私はいちおう科学を飯のタネとしているが、そんなデータ至上主義の堅物だろうが、己に対しては甘ったれのドアホである。
てなわけで、私は欲望のまま夕飯後にコンソメパンチの袋を破り、寝起きにはアルフォートをボリボリ噛みしめ、破滅への道をただひたすらに駆けていた。
ブックブク推進期間の心中
読者諸氏は思うだろうか。きっとヤツは日増しに増える体重が、恐怖で夜も眠れなかったに違いないと。
ところが当の本人は、「全然、まったく気にしていない」のであった。もちろん、増え続ける体重に気付いてたにもかかわらずだ。
なぜなら、くだんのドアホは体重増加を問題として捉えていなかった。問題がなければ恐怖のしようがない。つまり、ブックブクの過程にあっても、私はストレスフリーの日常を送っていたのだ。
とはいえ、「さすがにウエストがキツイのは問題でしょうよ」。ときたま、私の良心がそうささやいていた気もする。
これは確かにごもっともな指摘と思う。アグリーだ。ウエストがキツい、これはどう考えても問題だ。
だが不思議なことに、ジーンズが「まだ履ける」。その事実がある限りにおいて、キッツいことは私の中では問題提起に至らなかった。
つまり、「キッツいのは認めよう。で、何か問題でもあるわけ?」の心境だったのだ。
些末事は気にしない、そんな私のポジティブさが見事に現れた事例といえる。
これを開き直り、もしくは「見てみぬふり」と人は呼ぶらしい。
「見てみぬふり」の恐ろしさ
「見てみぬふり」、このリスクを正しく認識している人はどれだけいるのだろうか。
名著「文明崩壊」のジャレッド・ダイアモンドは本書のなかで、かつて栄華を誇った多くの文明が、悲惨な崩壊に至るまでの経緯を紹介している。
それらの直接要因はいずれも過剰な自然破壊にあるが、その根幹に共通するのが人々の「見てみぬふり」と解釈できる。
つまり、先人たちは自然破壊に気付いておきながら、その深刻な影響を「見てみぬふり」して全滅したのだ。
農地や燃料を求め続けた揚げ句、森林が失われ、ついには飢餓や越せない冬が到来するのだ。
だがそれらを認識した時点では手遅れだ。もはやジーンズは入らない。
凍える冬。ジーンズの履けない彼らは、下半身が丸出しだ。一人、また一人と寒さに倒れていったことだろう。
こうして、先人たちは自然破壊を、そして現代人の私は体重増加を、それぞれに「見てみぬふり」して崩壊の一途をたどった。
そう、私は歴史に学ばなかった。ウエストがキツくなっても、腹を引っ込めればまだ履ける。それでダメなら、ベルト穴をずらせばまだ履ける。
こうした哀しき安堵を繰り返し、コンソメパンチな日々を続けていたのだ。
愚かにもプレーンに加えて、ダブル味とトリプル味をも採用し、月月火水木金金、休むことなく禁忌のローテーションは加速した。
こうして、私はひたすらに大モンゴルを駆け抜けた。
大地は広い。遠くへ、もっと遠くへ、私はどこまでも行けそうな気がしていた。
神を信じない
さて、不幸にも先人たちの自然破壊は行くところまで突っ走り、結果として文明崩壊に至ってしまった。
そのトドメとなったのは、崩壊の最終場面において、彼らが課題解決を神に丸投げしたのが原因とされている。要は祈るばかりで何もしなかったのだ。
対してジーンズの入らない私には、祈る神がそもそもいない。いや、今はいないと言うのが正確だろうか。
私も過去には祈ったことがある。あれは出先でウンコが漏れそうなときだった。今後は「良い子」になりますから。そんな代償を差し出すほどの、神聖かつ切実な祈りだったのを記憶している。
ちなみにあれ以来、私は神に祈ることをしていない。きっと今後もしないだろう。
そう、あの時祈りは届かなかったのだ。私は死ぬまで「悪い子」のままに違いない。
ブックブクを認める方法
今思えば、あのコンソメ凶行軍に拍車をかけていたのは、我が家に体重計がなかったことが大きいだろう。
なぜなら、いくらジーンズがキツくとも、それは「太ったこと」に対する科学的なエビデンスにはなり得ないからだ。
そして他人ばかりか自分に対しても優しい私は、「どんまい」を惜しむことなく連呼できてしまう慈愛に満ちた存在と自負している。
これら甘やかし要因がシナジーした結果、私は「入らない」現実に直面してもなお、その事実から目を背け、「どんまい」ばかりを連呼していた。
実際、絶望のテンカウントが始まった段階においても、「もしかしたらジーンズが縮んだだけかもしれない」。そんな間の抜けた言い訳に安堵すら覚えていたのだ。
ちなみに、ここまで書いておいて恐縮だが、私はこんなドアホが科学者を名乗れてしまう、日本の将来が心配でならない。
だが、そんなドアホを現実に引き戻したのも、また科学であった。
私は「入らない」エビデンスを科学するべく、体重計を購入していた。
きっと、頭のどこかでは分かっていたのだ。ジーンズが縮んだせいではないことを。
ご存知のとおり、サイエンチストは数値を信じる。それがどんなに残酷な値であろうが、信じざるを得ないのだ。それが科学者としてのアイデンティティの源だからだ。
そして忘れもしないXデー。私は入手したての体重計に、何度も何度も昇降していた。もしかしたら測定誤差があるかもしれない。そんな虚しい願いを胸に、何度も何度も昇降していた。
しまいにゃ体重計をひっくり返し、電池を入れ替え、なおも真なるエビデンスを求め続けた。私はあのとき、泣いていたのだろうか。口ではハハハと言いながら。
そんな奇行を10分くらい続けたあとで、私はようやく現実を受け入れた。
ああ私は今、人生史上最高の到達点にいると。
認めよう、私は今、ブックブクだと。
ひとつのエビデンスを確認したサイエンチストは、そのまましばらく、残酷な測定機器の上にて惚けていた。
彼は全裸だった。服って意外と軽いんだな。そんなことを惚けながらに口にした。
それに応える者はいない。ただただ静かに、可愛いスーホが揺れていた。